緑内障は進行性で治らない病気です。進行するのを遅らせる、止めることが治療です。
正しい治療の仕方として、「治療をすぐに開始するな」というタイトルですが、疑問を浮かべるかもしれませんが、解説していきます。
ちなみに、中には「すぐにでも治療を開始する必要がある人」もいますので、
- 緑内障の分類が何か
- 緑内障による現在の視野障害、残存視機能がどの程度か
- 本当に緑内障による視野障害なのか
などを総合的に正しく判断する必要があります。
緑内障は、雑にやれば、まずは点眼を使うだけでよいので治療は簡単です。しかし、正しく診断し、年齢・残存視野・ADL・家族関係などを総合的に考えて治療を行う場合、なかなかに判断が難しい疾患です。
緑内障診療のスタイルでその眼科医の考察レベルがわかるな、と思えるほどに感じます。
緑内障の定義
そもそも緑内障とは「眼圧が原因で、視神経が障害され、視野が狭窄していく病気」のことです。
日本緑内障学会の緑内障診療ガイドラインでは下記のような記載となっています。
緑内障は,視神経と視野に特徴的変化を有し,通常,眼圧を十分に下降させることにより視神経障害を改善もしくは抑制しうる眼の機能的構造的異常を特徴とする疾患である.
緑内障診療ガイドライン第5版
ここで大切なのは
- 眼圧が原因で
というところです。障害される順序としては、
- 眼圧が原因で
- 網膜神経線維が障害され(網膜が菲薄化する)
- 視野障害が生じる
という流れになります。
なぜここが大切かというと、眼圧以外にも、視神経が障害されたり、網膜が菲薄化する疾患はいくらでもあります。眼圧が原因で起こったことでなければ、当たり前ですがその病気は緑内障ではありません。
視神経が障害されれば視野は障害を受けます。外傷で障害されれば外傷性視神経症、腫瘍などで圧迫されて障害されれば圧迫性視神経症、遺伝性疾患であればその遺伝性疾患が、網膜の障害から視野障害があればそれはその網膜の疾患が原因となります。
緑内障の治療の意味
眼圧が原因で、視野が障害される。
視野狭窄が高度になると、生活に支障がでる。
そうならないように進行を抑えるのが、治療です。
つまり、眼圧と視野、どっちが大事かというと、当たり前ですが視野です。眼圧は、視野の進行の程度を評価するための指標に過ぎません。
1回1回の眼圧の値を非常に気にする患者さんがいらっしゃいますが、あまり意味がありません。(これは、医師の説明の仕方にも原因があると思われます。)
眼圧は常に変動し、朝と夜でも異なり、季節でも異なり、座っているか寝ているかでも異なります。
眼圧が高くても、視野が悪化していなければ気にする必要はありません。見えなくなっていませんから。
逆に眼圧が低くても、眼圧によって視野が悪化していたら治療が不十分ということになり、更なる強い治療が必要です、そのままでは見えなくなってしまいますから。
つまり、視野狭窄を進行させないように、視野ベースに治療を考えることが本質です。しかし視野検査はその検査の性質上(時間がかかる)、頻繁に検査をすることが難しく、多くても年に3回程度です。
そのため、その視野検査の結果の経過を見ていくとともに、その間のおおよその眼圧を測定しておき、視野進行がある場合や、疑わしい場合には治療を強化しより眼圧を下げていく、ということが治療になります。
生存中に視機能を保たせる
そして緑内障の治療で一番大事なことは、
「その人が生きているうちに目が見えなくならないか、緑内障による視野障害で困らないか」です。
緑内障があっても、高齢で視野障害が軽度で、進行がゆっくりな人、寿命を迎えるまでに緑内障による視野障害で生活に支障がでないであろう人に、治療をする必要は必ずしもありません。(ただし視野が悪化してこないか、できる範囲でフォローは推奨します。)
必ずしも必要のない治療をしている時間の無駄と、薬剤・医療費の無駄と、通院・点眼にかかる患者さんや家族の負担を考慮して、点眼を開始しないという選択肢もあるということです。
緑内障は国内における視覚障害者となる原因疾患の第一位ですから、知っている一般の人は「緑内障=失明する病気」と認識している人もいます。一方で、眼科医側からも「失明原因の一位」というフレーズで強く印象を与える説明をしている可能性もあります。
緑内障の点眼は、視野障害の進行を遅らせるためのものであり、治療効果を実感するものではないため、離脱率が高いです。このような背景からも、しっかりと説明することは重要ですが、中には「目薬しないと失明しちゃうから」と、半ば強迫観念のような状態でずっと点眼だけは頑張っている、緑内障初期の高齢者の方なんかもたびたび見かけます。
離脱しないようしっかりとした説明も大切ですが、本当に点眼が必用な人なのかもよく検討した方がよいと思います。
視野障害、網膜菲薄があれば全て緑内障?視神経萎縮の鑑別
網膜から脳までの視路のどこの神経に異常がでても、それが神経細胞・軸索の障害であれば、順行性萎縮、逆行性萎縮により対応する神経細胞は萎縮していきます。
- 順行性萎縮:細胞体の障害で軸索が障害され萎縮する
- 逆行性萎縮:軸索の障害で細胞体が障害され萎縮する
緑内障に特徴的な視神経乳頭所見はありますが、そのような所見に乏しいときや、診察になれていない人だとわかりにくいことがあります。
例えばBRVO後の網膜の菲薄化からの視神経萎縮(網膜性萎縮:多くは部分的になるので鑑別可能)では、OCTマップによる網膜厚測定だけでは緑内障と区別がつかないこともあります。
視神経乳頭より中枢の障害では、逆行性に視神経乳頭は萎縮し蒼白化し陥凹もできて、網膜も菲薄化し(単性視神経萎縮)、所見が似ている場合もあります。
緑内障性視神経萎縮では、網膜神経線維層の菲薄化が先行し、視神経乳頭の陥凹が縦方向(深く)、横方向(リムが薄く)に広がり、最終的に蒼白化していきます。白色化より陥凹が先行すること、陥凹の辺縁部にノッチがあること、Bjerrum領域に相当する障害が多いことなどの特徴から鑑別は可能ですが、ときに難しいこともあります。
視野が進行しているのか、進行しているのであれば眼圧によって進行しているのかを確認しないと緑内障とは言えないはずですよね。
無治療時のベース測定の重要さ
緑内障のうちの開放隅角緑内障の多くは、たまたま眼底健診で視神経乳頭異常を指摘されたり、たまたま別のことで受診したときに眼底を見てみたら緑内障がありそうだ、というような「たまたま」パターンと、ほとんど病院受診してこなかった人が最近見え方が悪いと感じ受診し、診てみたらかなり進行していた緑内障だった、という「残念」パターンが多いです。
後者では緑内障の視野の状況に応じて、末期の緑内障であれば視機能が悪化しないように早急に治療を開始してよいです。ベースラインを測って無治療でいるうちに悪化させるより、治療を先決してよいと思われます。
一方前者のパターン、たまたま見つかった人の多くは初期の緑内障です。では、さっそく点眼治療を開始しますか?もちろん、治療開始すべきではありません。年齢、リスクにもよりますが、まずはベースラインを測定していきます。
後期例など特に治療開始を急ぐ必要のある例でない限り,治療開始の前に眼圧,隅角,眼底,視野などのベースラインデータを十分に把握しておくことが望ましい.
緑内障診療ガイドライン第5版(p107)
ベースラインの測り方
以下のようなことを治療開始前に診ていく必要があります。
- 病型、年齢その他のリスク因子
- ベースラインの眼圧がいくらなのか
- ベースラインの視野がどの程度なのか
- 無治療での視野狭窄のスピードがどれくらいなのか(これは残存視野に余裕がある場合に検討してもよい)
①~③は緑内障診療ガイドライン第5版|日本緑内障学会にも記載があります。治療を開始する上で、どの程度の目標眼圧にするか決める要素です。
病型、年齢、リスク因子
これは診察、問診にて。
ベースラインの眼圧
ベースラインの眼圧の測定回数はガイドラインに具体的な回数の記載は見当たりませんでしたが、3~5回程度測ります。眼圧は日内変動、季節変動、医者の測定手技による誤差、診察時以外の眼圧は不明など、不確定要素があります。
それらをできるだけ平均化して誤差を少なくするために、眼圧のベースラインを測る上で3~5回程度測定します。
ベースラインの視野
視野進行の有無が治療効果の判定に用いるわけですから、治療開始前の視野を測る必要があります。
視野検査は初回より2回目以降のほうが慣れて上手くできることが多いこと、その日の体調などにより検査結果の正確さは変わります。つまり、ベースラインの視野も本来は1回では判断ができません。(測定結果からある程度うまくできているかは判断できますが)
ガイドラインにも「視野などのベースラインを十分に把握しておく」と書かれていますが、どれくらいの期間にどれくらいの頻度で行うかの記載はありません。一方、視野進行の判定は最低5回以上で行うことが推奨されています。
では、ベースラインも5回程度行ったほうがよいのか?というと、さすがに短期間に高頻度の視野検査を行うのは現実的には難しいです。(視野検査は時間がかかる検査であり、行うとしても多くても年3回前後です)
一方で、期間をあけて複数回行ったとしても、それは果たしてベースラインなのかという問題も生じます。どちらかと言うと、もし進行していたら進行と判断すべきな気もします。
ガイドラインもそのあたりがやや曖昧であり、ベースラインが重要と言うわりに、そのベースラインの具体的な測定方法が未記載ではあります。
無治療での視野進行のスピード
これは必ずしも測る必要はなく、早急に治療を始めたほうがよい症例は治療を開始してください。あくまで、充分な残存視野がある際に、検討してもよい内容ということです。ガイドラインには記載はありません。
これを考える理由としては、以下の理由があります。
- そもそも緑内障性視神経症以外の可能性がある(診断が誤っている可能性)
- その場合は進行しない可能性がある(進行する疾患の可能性もありますが)
- 無治療での進行速度を測ることで、逆算的に何歳頃発症したのかが分かる(必ずしも必要な情報ではないが、その速度が分かれば場合によっては無治療での経過観察でもよい場合もある)
- 点眼にて眼圧が下がって進行速度が下がっていたら治療効果がありと直接的に判断できる
- 逆に無治療での進行速度が分からなければ、それが点眼での効果か判断できない(点眼してなくても進行していなかったかもしれない)
- そもそも進行速度が遅いのであれば、年齢等考慮して無治療でもよい場合もある
治療前の進行スピードを知る必要はなく、治療後(点眼開始後)の進行スピードを見ればよいという意見もありますが、たしかにそれだけでもよいです。ただしその場合に必要なのは、点眼開始後に視野障害が全然進まなかった場合、点眼をやめる選択を取れるかどうか、ということです。
基本的に緑内障は進行性の病気であり、その進行スピードを抑えるために点眼を使うので、基本的にはずっと続ける治療です。特に理由がなければ点眼は継続するのが普通ですが、視野障害が進行しなかった場合はその理由になります。
もともと緑内障であれば、点眼をやめたことにより眼圧は多少上昇しますので、視野障害は多少進行しやすくなります。それでも進行しないのであれば、本当に緑内障なのかも考える必要もありますが、そもそも点眼を開始しなくてよかったパターンと言えますよね。
ガイドラインにも点眼治療の中止に関することは書かれています。
また、「視野進行は最低5回以上の検査結果から判断する」ということに関して、おそらく多くの施設で視野検査は多くても4-6か月に1度程度の頻度だと思います。つまり5回行うのに、早くても2年近くかかります。視野進行を判定するのに2年以上かけるのであれば、治療を開始する前に年3回程度視野検査をし、ベースラインとして測りつつ視野進行がないか、あればその進行速度を測ってから治療を開始してもよいと思います。
このことに言及する理由としては、「この患者さんに緑内障点眼は必要なのか?不要ではないか?」という事例にかなり遭遇するからです。患者さんの中には必要ではないかもしれない緑内障点眼の治療を、毎日毎日頑張ってずっと続けている人もいるということです。
緑内障点眼は普通は急にやめたりしない薬剤です。もちろん中止してはいけない薬ということではありませんが、普通の眼科医はそのまま継続で処方し続けます。そのような薬を、不十分な判断なままで開始することは、たしかに緑内障としての進行はしにくくなるかもしれないけれど、その他の負担などを考慮していなかったり、ただ単に処方開始している何も考えていない医者という印象を受けます。
ただし先ほども述べたように、視野狭窄が高度な人や進行リスクが高い人には、ベースラインを測っている間に進行させるより、進行させないように治療を開始したほうが本人にとってもよいので、治療を始めます。
また、基本的に緑内障を周辺視野から障害されますが、中には黄斑線維束が早期に障害されて自覚症状が出る人もいます。そのような人はベースラインフォロー中に自覚が悪化する場合もあり得るので、本人と相談の上、治療を早めに開始してもよいと思います。ただしその場合は(それ以外の場合も含みますが)、治療開始後の視野フォローで、長期間進行傾向がないのであれば一度点眼中止も考慮に入れるべきだと思います。
要は、ケースバイケース、ということです。
緑内障以外にも医療はケースバイケースばかりですが、緑内障は治療を始めたら基本的にはずっと続けるもの、という点から、治療開始前に充分に検討する必要があるということです。
まとめ
- 緑内障で眼圧は大事だけど、一番大事なのは視野
- 視野に着目し、それが悪化しているのであれば眼圧を下げる必要がある
- 緑内障以外でも視神経乳頭萎縮、陥凹、網膜菲薄化は起こる
- 診断してもすぐに治療を開始してはいけない(ベースを測定する)
- 重症例ではその限りではない
- 「緑内障点眼は一生続けなきゃいけないもの」とは限らない
緑内障は本当にしっかり治療できている人とそうでない人がはっきり別れると思います。ベースラインすら測られていない患者も多いし、緑内障じゃなさそうな視神経萎縮に永遠と点眼を出されている人もいます。
緑内障は失明原因の第一位ということはほとんどの眼科医が知っているし、そのことを説明する場合も多いと思います。しかし、そう言うわりに自分はまともな治療ができていないパターンが往々にしてあると思われます。それらは後任の眼科医が見て初めて分かるのであり、そういう目で見ない限り、曖昧な治療が蔓延してしまうと思います。
そういった意味を含めて、「すぐに治療を開始するな」という内容でした。




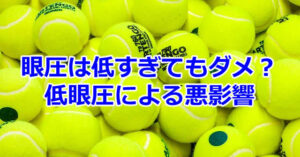
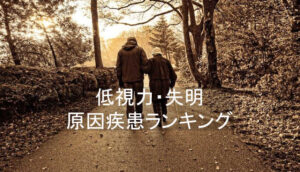
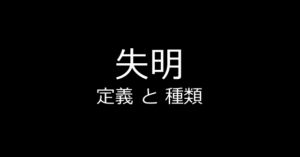


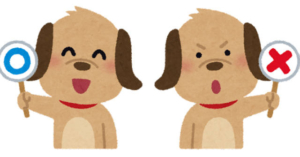


コメント