待ち時間は、「患者人数」と「患者1人にかかる診察時間」で決まります。自分の前に患者が20人いて、1人あたり3分ぐらいかかっている場合、自分の番になるまでには20×3で約60分かかります。
今回はこの待ち時間対策としての、「患者1人にかかる診察時間」をできるだけ短くするための対策を考察していきます。これには医療者側だけでなく、患者側の意識も大切になってくる内容です。そのため、本記事では「医者ができること」、「患者ができること」と分けて記載していきます。
待ち時間が長くなる根本的な原因
繰り返しになりますが、病院の待ち時間は
- 患者数
- 1人あたりの診察時間
で決まります。したがって、待ち時間を短くするためには、患者数を少なく、1人あたりの診察時間を短くすることが対策になります。患者数を少なくするためには、患者を分散させる目的で診療時間を長くしたり、診療日を増やしたり、予約システムで偏らないようにしたりなど、いろいろな対策はありますが、今回は診察時間を短くする方法に関して書いていきます。
待ち時間が長くなる原因と対策 医者側
外来の待ち時間が長くなる原因として、医者側に原因がある内容としては
- 診察スピードが遅い
- 診察自体が遅い
- 説明が長い、丁寧過ぎる
- カルテ操作が遅い
- 次の患者を呼ぶまでの時間が長い
- 予習をしていない
- 事前に方針を決めていない
- 事前に検査結果を確認していない
などがあると思います。
診察スピードが遅い
診察スピードが遅い原因としては
- 診察自体が遅い
- 説明が長い、丁寧過ぎる
- カルテ操作が遅い
などがあります。診察自体が遅い点に関しては、若手医師の場合はある程度仕方ないかもしれませんが、これは医者としての技量の問題になるので、なるべく早く習得してスムーズに診察を行えるようにしましょう。
説明が長い点に関しては、簡潔すぎる説明は返って患者さんの不満につながることもあるので難しいところですが、丁寧過ぎる説明も診察時間が長くなる原因となります。ある程度要点をしぼって患者さんの容態を聞き、わかり易い言葉で簡潔に説明することが大切です。
カルテ操作に関しては、現在は電子カルテのところが多いため、特に高齢の医者の場合、タイピングが遅かったり、パソコン操作がわからなかったり、時間がかかる傾向があると思います。また、非常勤医師など、その病院のカルテをたまにしか使わない医者の場合、カルテ操作に慣れていないため時間がかかる可能性があります。なるべく早くカルテ操作になれ、時間をかけないようにする、または医療クラークを雇うなどの方法があります。
- 30人の患者がいて、患者一人あたり平均3分で診察した場合、90分(1時間半)
- 30人の患者がいて、患者一人あたり平均5分で診察した場合、150分(2時間半)
- 30人の患者がいて、患者一人あたり平均10分で診察した場合、300分(5時間)
診察スピードは遅ければ遅いだけ、患者さんは待つはめになり、自分の仕事が終わるのも遅くなります。一人あたりの診察時間を短くできるように努力しましょう。
次の患者を呼ぶまでの時間が長い
実際に診察をしている時間以外に、患者さんが診察室に出入りする時間も考慮しましょう。
患者さんを診察室に呼んでも、患者さんが診察室に入ってくるまでには時間がかかります。前の患者さんが診察室を出て、次の患者さんのカルテを開いて、内容を確認してから患者さんを呼んでも、患者さんが診察室に入って着席し、診察を開始するまでには時間がかかるのです。
診察室近くで待機している患者さんの場合、数秒で診察室に入ることもありますが、診察室から遠い場所で待っている患者さんもいれば、足腰が悪く移動に時間がかかる患者さん、音声で呼び出しても耳が悪くて気が付かない患者さんもいます。
すなわち、前の患者さんが診察室を出たら、できるかぎり早く次の患者さんを呼び入れるようにし、患者さんが診察室に入ってくるまでの間にカルテを確認するようにすると、効率がよいです。
診察室の出入りにかかる短い時間でも、患者数が多ければ大きく時間効率に関わります。(60人の患者さんがいて、入れ替えに1人30秒かかる場合、入れ替えだけで30分かかることになります。)
患者さんが退室してからもカルテを書くことは多いとは思いますが、前の人のカルテ記入が終わったら、できるだけ早く次の患者さんを呼び、患者さんが入ってくるまでの間にカルテを確認しましょう。
予習をしていない
病歴が複雑な患者さんなどは、事前にカルテを確認できるのであればしておくと対応が早くできます。もちろん、とっさに全て対応できるレベルの知識があれば話は別ですが、検査結果なども時間があれば先に見ておいたほうがその場で見なくて済み、早く対応できます。
特に若手の医師は予習して方針を決めておくことで、スムーズな診察ができることが多くなると思います。
待ち時間が長くなる原因と対策 患者側
待ち時間が長くなる原因として、患者側にも原因がある内容として
- 診察室への入退室が遅い
- 話が長い
- 医者に聞きたいことがまとまっていない
- 医者からの治療方針の提案に迷い続ける
- 残薬数を確認していない
などがあると思います。
診察室への入退室が遅い
これは、足腰が悪い人、耳が遠い人などもいるため、いたしかたない部分もあります。しかし、自分の診察の番号を確認して、近づいてきたら診察室の近くで待つようにするだけで、待ち時間短縮に繋がります。
診察室に呼ばれてから、診察室から非常に遠いところからゆっくりと診察室へ向かうのと、すぐ近くで待っていて診察室に向かうのとでは、それなりに時間の差が生まれます。
もちろん、席が空いてないなどの理由で難しい場合もあります。可能であれば、診察の時間が近づいたらできるだけ診察室の近くで待つようにしましょう。
話が長い
やっと自分の番が来たのだから、話したくなる気持ちもわかります。病状に関しては話してもらわないとわかりませんので、ぜひ話してください。
しかし、こちらとしては質問したことに関する返答が欲しいのです。昔々のストーリーからお話される方や、全く関係がない返答が来たりする方がいらっしゃいますが、時間だけたってしまいあまり重要ではありません。
また、おしゃべりは医者側がしてくれそうな感じであればしてもよいですが、あまり関係のないことを長々としゃべってしまうと、結局それ以降の患者さんの待ち時間が長くなります。
たくさん待ったのだからしゃべりたい、というのもわかりますが、次の人以降をさらに待たせてしまうため、必要以上におしゃべりをするのは、少しご配慮していただけると助かります。
医者に聞きたいことがまとまっていない
「何か聞きたいことはありますか?」
と聞いてくれる医者はやさしいと思います。(聞かないでさっさと終えてしまう医者はたくさんいます)
しかし、聞いておいてなんですが、聞きたいことがあるのかないのかはっきりしなかったり、聞きたいことがまとまっていなかったり、聞きたいことを書いたメモがどこかにいってしまって探されたりされると、時間がかかってしまいます。
質問をできるだけ簡潔にまとめていただいて、2-3点程度までにしていただけるとありがたいです。
医者からの治療方針の提案に迷い続ける
検査や診察の結果の説明を受けて、それに対して治療などの方針の説明があると思います。現代では基本的に医療はIC(インフォームドコンセント)という用語があり、「医療者側が治療などの説明をした上で、患者側が選択し同意する」という形をとります。
つまり、治療の決定権は患者側にあります。患者さんがどうしたいか決定してもらえないと、治療はできません。
これもいきなりどうするか選べと言われても困る、というのもよくわかります。その場合は「どれがいいか?」と素直に聞いてもらえれば、医者から提案もしてくれるでしょう。
その場でなかなか決めれない場合は、後ほど診察室に来てもらうか、後日などでもよい場合もあります。迷いやすい人の場合、同席者がいると結構すんなり決めてくれることも多いです。どうしようかずっと診察室で悩まれると、時間がかかってしまい、結局それ以降の患者さんの待ち時間が長くなることにつながってしまいます。
残薬数を確認していない
内科の薬は日数で出されることがほとんどであり、飲み忘れがなければ残薬数が大きく変化することはありません。
一方、眼科の点眼薬は、毎回上手に1滴ずつさせる人は別ですが、慣れないと何滴も点眼してしまったり、残数が結構ばらつきます。
点眼薬の残りがどれくらいあるか、次回の診察までに点眼薬が何本あれば足りるか、をあらかじめ確認していただけると、素早く対応できます。
まとめ
- 医者ができること
- 診察技術・スピードをあげる
- わかりやすく簡潔に説明できるようにする
- 次の患者さんを早く呼ぶ
- 予習をする
- 患者さんができること
- 診察の番号が近くなったら診察室の近くで待つ
- 関係ない話を話し過ぎない
- 聞きたいことはあらかじめ決めておく
- 治療方針に悩む場合は後日でもよい
- 残薬数を事前に確認しておく
医者側が診察技術やスピードをあげる努力をして、混まない外来を提供できるように努めるのはあたりまえのことです。ただし現実的には、それだけではどうしようもないほど患者数がいることもあります。
一方、患者さん側は特段何をしろということはないですが、多少の気を使っていただければありがたいという話です。自分の番号が近くなったら診察室の近くで待つ、お喋りしすぎない、残薬数を確認しておく、自分で判断がすぐできない場合は身近な人に同席してもらう、などがあります。
今回は患者数は多いことが前提で、その上で、待ち時間を減らす方法として、1人あたりの診療時間をより短くする方法は何か?という内容でした。
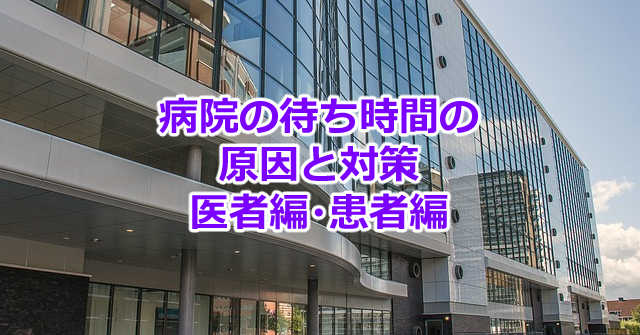
コメント